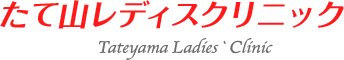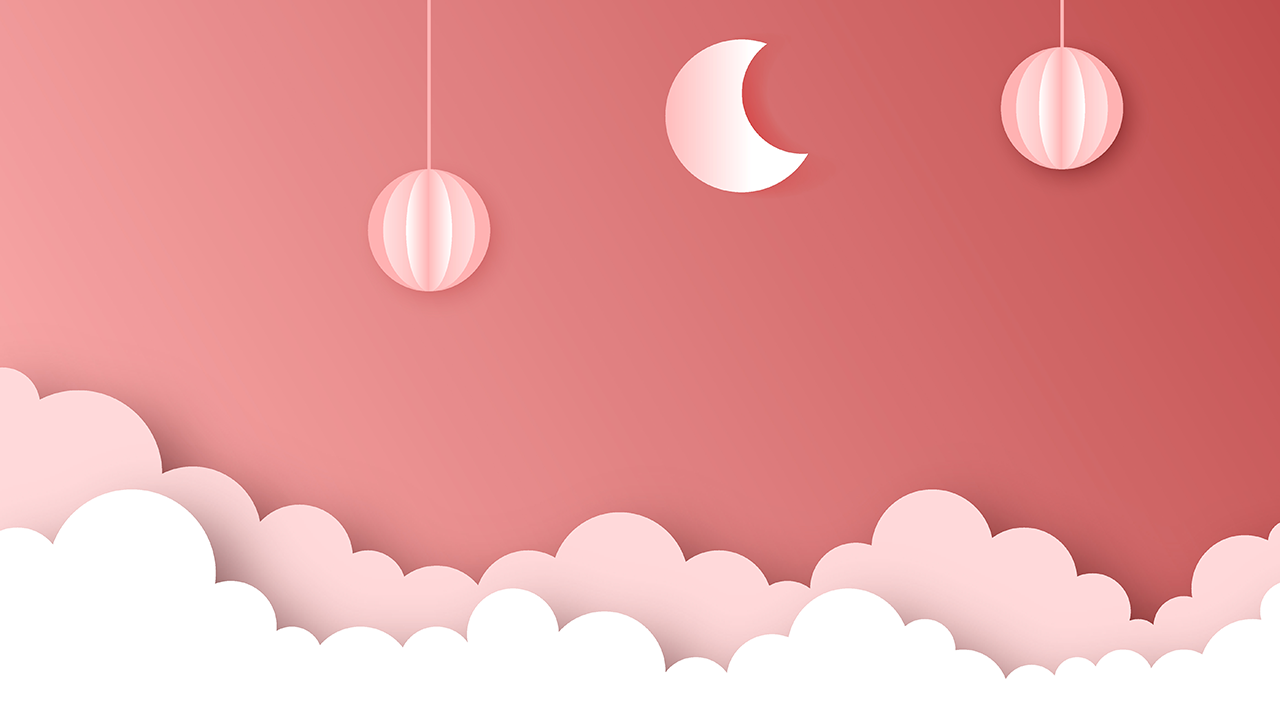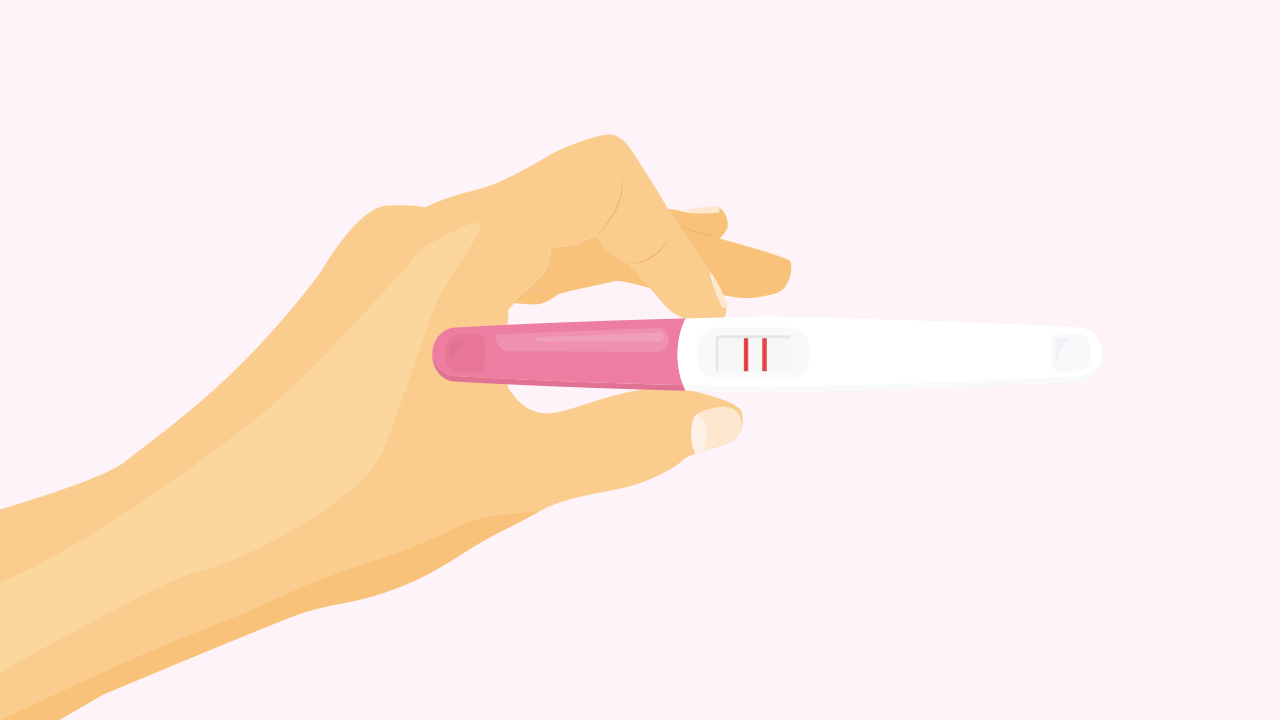卵性による分類として2卵性双胎と1卵性双胎があります。
多胎妊娠(双子、三つ子、四つ子等)は妊娠経過や出産過程において母児共に負担やリスクが高くなるため注意が必要です。
出産を希望される方は勿論ですが、出産に関して迷われている方も、早い段階で産科・産婦人科の病院を受診して、妊娠週数と双胎妊娠や異常妊娠がないかどうかを含めて妊娠状態を正確に確認することが大切です。
超音波検査の結果、もし双子であった場合は、妊娠初期の妊娠8週~妊娠10週頃までに膜性診断を行っておくことが重要です。
双子の中絶は、身体的・精神的に大きな負担を伴うため、正しい知識と早めの判断が大切です。
ひとりで悩まずご相談ください
03-3408-55261.双子の中絶について
双子(双胎)の種類には卵性による二卵性双胎、一卵性双胎があります。
卵性による2卵性双胎と1卵性双胎の分類のほかに、膜性診断による双胎妊娠分類があります。
膜性診断により一絨毛膜一羊膜双胎の場合は、赤ちゃんと妊婦である母親に妊娠中に異常が生じるリスクが生じます。
中絶を望んでいた方でも途中で出産に変更される方もおられますので、双胎妊娠の場合は、初期妊娠の時に膜性診断をおこなっておくことが大切です。
妊娠10週までには膜性診断をするのが望ましいです。妊娠週数が進むと、診断が難しくなっていきます。
当院では、双子妊娠の減胎手術(塩化カリウムを注入して胎児を減らす手術)は行なっていません。 双胎妊娠の場合は11週から14週頃までに膜性診断をしておくことが大切です。
膜性診断とは
胎盤の元になる双胎の2枚の絨毛膜と、胎児を包む双胎の2枚の羊膜の、膜の数と構造を診断するのが膜性診断で、2絨毛膜2羊膜が正常です。
卵子が排卵受精して受精卵となり、細胞分裂を繰り返して成長していくと、胎盤の元である「絨毛膜」と、胎児と羊水を包んでいる「羊膜」が形成されていきます。
絨毛膜が2つで羊膜も2つの場合が2絨毛膜2羊膜双胎で、絨毛が1つで羊膜が2つの場合が1絨毛膜2羊膜双胎です。絨毛膜が1つで羊膜が1つの場合が1絨毛膜1羊膜双胎となります。
膜性診断が重要なのは、1絨毛膜1羊膜双胎の場合母体にも影響することがあることと、妊娠初期の超音波で診断されるからです。
そのため、出産を迷われている方や中絶手術から出産に変更される方もおられますので、妊娠初期に膜性診断をされておく必要があります。
2.双子の中絶を判断する時期
さまざまなご事情や理由から、妊娠継続ができないと考えることは女性にとって大変大きな決断になります。不安や心配な気持ちがあるのは当然のことです。
お一人で悩みを抱えず、ご両親やパートナーとも十分にご相談ください。
当院では経験豊富な医師の院長とナースとスタッフがご相談をお受けしております。
受診にはご予約をお願いします。
法律上は、通常の中絶と同様、双子の中絶も21週まで実施できることになっていますが、多胎妊娠をした時点で、単胎妊娠よりも母体への影響が大きいです。
人工妊娠中絶手術を考えている場合は早めに中絶手術をするように判断したほうが母体への負担は少ないといえます。
妊娠初期と妊娠中期では手術方法やリスクが異なり、双子ならではの注意点も加わってきます。
妊娠9週以下でしたら経口中絶薬による中絶も可能です。 そのため妊娠12週を超えた「中期中絶」よりも、妊娠11週以下の「初期中絶」での処置をお勧めします。
手術後は術後検診を受け、身体と心の回復に努めましょう。必要なときは医師や周囲に相談し、一人で抱え込まないことが大切です。自身の選択を大切にし、安心して前に進めるようにサポートを活用してください。
妊娠に気がつきましたら、単胎妊娠であっても多胎妊娠であっても、妊娠週数と妊娠状態を正しく確認することがとても大切なことですので、なるべく早く母体保護法指定医を標榜している産科・産婦人科医院を受診することをおすすめします。
3.双子の中絶手術の流れ
当院では、予約日当日にご来院後、問診票をご記入いただきます。
術前検査の超音波検査、血液検査、感染症検査、Rh式血液型不適合妊娠等、必要な検査を受けていただきます。
超音波検査で双胎が確認されましたら、膜性診断を行なっております。
合併症などの問題がなければ、双子の中絶手術のご相談をお受けしております。
ご本人様と男性パートナーでよく話し合って、中絶手術希望とご決断された場合には、母体の負担を少なくするためにも、早めに医療機関を受診して妊娠状態を把握することをおすすめします。
双子の中絶手術の方法は、単胎の中絶手術の場合と基本的にはほぼ同様です。
中絶手術の流れ
(1) 相談・予約
お電話かWebより予約をお願いします。
初診日当日に中絶手術をご希望の方は、Web予約だけでは予約は完了していません。
診療時間内に受付までお電話をお願いしております。お電話で前日の過ごし方や当日の持ち物、注意事項などの詳細をお話しさせていただきます。
持ち物
・保険証(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードも可)
・同意書と印鑑(既婚者の場合は法律上必須)
・夜用ナプキン2枚
・生理用ショーツ1枚
・手術費用(クレジット払いご希望の方はクレジットカード)
・コンタクトレンズの方はメガネ
▼関連動画
(2) 初診日当日(来院)
予約日当日は、午前中の指定時間にご来院ください。 問診票にご記入いただき、各種検査を実施します。
・超音波検査(エコー)
・血液検査・感染症検査 ・Rh血液型不適合妊娠の検査
・超音波で双胎妊娠が確認されたら膜性診断
妊娠週数と手術方法
初期中絶(妊娠11週6 日まで) 吸引法(EVAまたは MVA)で実施します。
痛みのある術前処置は不要で、日帰り手術が可能です。
来院から約3時間程度でご帰宅いただけます。
手術中の麻酔は「静脈麻酔」と「笑気麻酔」を併用しています。
「笑気麻酔」が苦手な方の場合は省くことができます。手術中は眠ったままでリラックスした状態で手術を受けることができます。手術中の痛みはほとんどありません。
中期中絶(妊娠12〜21週6日まで) 妊娠14週以降は分娩法になります。
分娩法では、手術前日に子宮頸管拡張の術前処置が必要です。
翌日、子宮収縮剤で陣痛を起こして出産します。
術後は1週間以内に「死産届」「死産証書」を役所に提出し、「死胎火葬許可証」を発行してもらいます。双胎の場合は、それぞれ2通必要です。
健康保険加入者は「出産育児一時金制度」の適用があります。申請方法など詳細はご来院時にご説明しています。
費用について
当院の中絶費用は、一括のお支払いです。
手術に必要な項目は合計され、一括費用に含まれております。
費用に含まれる項目
・初診料
・診察料
・検査料
・手術料
・麻酔料
・術後1回目の検診料
・消費税
・永代供養
・火葬埋葬代(中期中絶のみ)
双子を中絶する場合の費用は、追加費用が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
▼関連動画
母体保護法指定医
当院の院長は母体保護法指定医、麻酔科標榜医です。
手術は、看護師との連携で全身状態を細かく確認しながら進めております。
安全性の高い、清潔でスムーズな手術を行なっております。
4.双子を中絶するときのリスク
「双子や多胎妊娠」の中絶手術の方法は「単体妊娠」の胎児の手術と基本的にはほとんど同じですが、「初期中絶」と「中期中絶」で注意点が違ってきます。
また合併症があるケースではリスクは大きくなってきます。
「初期中絶」の場合
「妊娠初期」で問題となるのは、筋腫合併妊娠や子宮の弓状子宮、双角子宮、重複子宮など子宮に形態異常があった場合に、双胎の一方のみを吸引してもう片方を見逃すことがない様にすることです。
ごく特殊で稀なケースですが、双子妊娠で一方が子宮内妊娠で他方が子宮外の異所性妊娠の場合は、子宮内の中絶手術を施行しても、もう一人の子宮外妊娠が存在することになります。予防・予知は難しく、防ぐためには術後1週間前後の再診のご来院が重要で、経過を慎重に観察することになります。
「中期中絶」の場合
中期妊娠の場合は初期妊娠よりも胎児が生長しているため、同じ週数でも単体妊娠の場合よりも双子の胎児を合わせて大きくなっていることに対する注意が必要です。
既往の帝王切開分娩後や子宮筋腫合併妊娠の場合は、手術後の弛緩出血による出血量の増加や子宮収縮による痛み症状の出現に注意が必要です。
また、双子を別々に娩出させることの必要性も大切です。
中期中絶の場合は、手術後1週間以内に役所に提出する「死産届」や「死産証書」も2通作成し、「火葬埋葬許可証」も2通発行してもらいます。
健康保険に加入している方は「出産育児一時金制度」の対象となります。
5.術後検診で不安の残らないアフターフォロー
手術当日は麻酔の影響が残っているため、自転車に乗ることと、ご自分でお車を運転することはできません。未成年の方は付き添いの方や親権者の方がいらっしゃると安心です。
手術後は、無理をせず心身ともにゆっくり安静にしてお過ごしください。
発熱等がなければ、手術当日からシャワーをご使用しても大丈夫です。
個人差はありますが、ほとんどの方が順調に回復して翌日から普段通りお仕事ができることが多いです。
術後の少量出血・腹痛・発熱などの症状には個人差があります。
処方されたお薬の服用で症状は改善することが多いです。
市販のドラッグストア等で購入できる解熱・鎮痛剤の内服薬をご利用されても結構です。
原則として術後1週間前後に診察の再診にご来院いただいています。
手術が完全に終わっていること、術後の症状についての対策、そして次回の妊娠には今回の中絶手術は影響しないこと等のご説明を行っています。
不安や心配が残らない様にフォローを行っています。術後検診は必ず受診するようにしてください。
*術後の検診料の費用はかかりません。
手術後には様々な症状が生じます。
主な症状として、腹痛、出血や微熱がありますが、これらについては「手術後におこりうるリスク」の項で詳細しております。
通常通りの中絶手術を受けたことが原因で次回に不妊症になることはありません。
次回も妊娠、分娩して子どもを持つことはできます。
中絶後の避妊にはピル服用や避妊リング(ミレーナ)などがあります。希望される方は当院のスタッフにお尋ねください。
術後はホームページでのフォローを行っています。
当院で手術を施行された方はお電話での対応も行っております。
6.おわりに
双子の中絶は、早期受診・正確な膜性診断・母体保護法指定医のもとでの適切な手術が安全確保の鍵です。
初期なら日帰り吸引法で身体的負担を抑えられ、中期でも分娩法に熟練した施設を選べばリスクは最小限で済みます。
術後は必ず再診を受け、身体と心の回復を第一に過ごしましょう。
悩んだときは一人で抱え込まず、医師・看護師・身近な人に相談してください。
自分の選択を尊重し、安心して次の一歩を踏み出せるようサポート体制を活用することが、中絶における最大のポイントです。